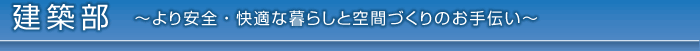2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(後に津波による大災害等を含めて「東日本大震災」と呼称)では、とてつもなくたくさんの方々が被害に遭いました。突然の不幸に見舞われお亡くなりになりました方々に対し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
今回の地震以前にも幾度となく日本を襲った大きな地震を経て、建物の耐震化基準が厳しくなって来ています。以下に主な地震と建築法規の改正を記載します。
| 1923年 (大正12年) |
関東大震災 | マグニチュード7.9 全壊家屋128,000棟、死者142,000人。 |
|---|---|---|
| 1924年 | 市街地建築物法改正 | 大震災の教訓から、耐震規定が初めて盛り込まれた。筋かいなどの耐震規定が新設。 |
| 1948年 (昭和23年) |
福井地震 | マグニチュード7.1 死者3,769人、家屋倒壊36,184、半壊11,816、焼失3,851、土木構造物の被害も大(当時福井県の人口は37万人) |
| 1950年 (昭和25年) |
建築基準法制定 | 筋交い・耐力壁、XY方向の必要壁量を規定。床面積に応じて必要な筋かいを入れる「壁量規定」が定められた。 |
| 1959年 | 建築基準法の改正 | 防火規定の強化。 壁量規定が強化。 |
| 1964年 (昭和39年) |
新潟地震 | マグニチュード7.5 死者26人、家屋全半壊・焼失8,600戸。地盤の液状化と津波発生(高さ4~5m)。 |
| 1968年 (昭和43年) |
十勝沖地震(三陸沖) | マグニチュード7.9 津波発生。死者49人・不明3人、建物全壊673棟・半壊3,004棟・全焼13棟・半焼13件・床上浸水・床下浸水・一部破損15,697戸、水田・畑の被害、道路損壊・橋流失・堤防決壊・山崩れ・鉄軌道(線路)被害、船舶沈没・流失等の被害が生じた。 |
| 1971年 | 建築基準法施行令改正 | 鉄筋コンクリート造りの柱のせん断補強規定の強化。木造住宅の基礎の布基礎化。 |
| 1978年 (昭和53年) |
宮城県沖地震 | マグニチュード7.4 震度5(仙台市)。死者13人、重軽傷者9,300人、住家の全半壊が4,200戸 |
| 1981年 (昭和56年) |
建築基準法施行令大改正(新耐震設計基準) | 耐震設計基準が大幅に改正、現在の新耐震設計基準が設けられた。新基準の住宅は阪神・淡路大震災においても被害は小。 木造住宅においては壁量規定の見直し。構造用合板やせっこうボード等の面材を張った壁などが追加された。 床面積あたりの必要壁長さや、軸組の種類・倍率が改定された。 |
| 1993年 (平成5年) |
北海道南西沖地震 | マグニチュード7.8 推定震度6(烈震) 30.5mの津波発生(奥尻島)。190棟焼失。死者202人、29人が行方不明。(奥尻島だけで、172人の死者、27人の行方不明者) |
| 1995年 (平成7年) |
兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) |
 兵庫県南部(神戸市、西宮市、芦屋市、淡路島)。マグニチュード7.3。神戸が震度7(激震)、淡路島が同6(烈震)。死者5,450人を超え、負傷者は26,800人以上。家屋、ビルなどの損壊、焼失、流出は約10万件。 兵庫県南部(神戸市、西宮市、芦屋市、淡路島)。マグニチュード7.3。神戸が震度7(激震)、淡路島が同6(烈震)。死者5,450人を超え、負傷者は26,800人以上。家屋、ビルなどの損壊、焼失、流出は約10万件。 |
| 1995年 | 建築基準法の改正 | 接合金物(土台緊結、継手・仕口の緊結)の奨励。 耐震改修促進法が施行され、1981年(昭和56年)以前の建物(新耐震基準以前の建物)には 耐震診断が義務づけられた。 |
| 2000年 (平成12年) |
鳥取西部地震 | マグニチュード7.3 震度6強 死者なし。液状化による被害。 |
| 2000年 (平成12年) |
建築基準法の改正 | 木造住宅において、 1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査が事実上義務化に。 改正の要点 ・地耐力に応じた基礎構造が規定され、地耐力の調査が事実上義務化となる。 ・地耐力20kN未満・・・基礎杭 20~30kN・・・基礎杭またはベタ基礎 30kN以上・・・布基礎も可能 2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。 改正の要点 ・筋かいの端部と耐力壁の脇の柱頭・柱脚の仕様が明確になる。 ・壁倍率の高い壁の端部や出隅などの柱脚ではホールダウン金物が必須になる。 3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。 改正の要点 ・壁配置の簡易計算(四分割法、壁量充足率・壁率比)、もしくは、偏心率の計算が必要となる。 ・仕様規定に沿って設計する場合壁配置の簡易計算をする。 |
| 2004年 | 新潟県中越地震 | M 6.8、震度7。死者68人。震度6弱以上の余震を4回観測。 |
| 2007年 | 能登半島地震 | M 6.9 震度6強。死者1人。 |
| 2007年 7月16日 |
新潟県中越沖地震 | M 6.8 震度6強家屋倒壊や土砂崩れなどの被害。死者15人。最大1mの津波も観測。 |
| 2007年 | 建築基準法改正 | 構造耐力規定改正等 建築確認の厳格化。 |
| 2008年 (平成20年) |
岩手・宮城内陸地震 | マグニチュード7.2 震度6強 死者17名 行方不明6名 負傷者448名 土砂災害(土石流、地すべり、がけ崩れなど)が発生。 |
| 2011年 (平成23年) |
東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) | M 9.0 震度7(宮城県栗原市) 当地震による日本国内の被害は、地震そのものによる被害に加えて津波・火災・液状化現象・福島第一原子力発電所事故・大規模停電など多岐に渡り、警察庁発表(平成23年11月11日現在)による死者及び(届出があった)行方不明者の数は、合わせて約1万9千5百人で、津波被害を受けた東北地方の太平洋沿岸、宮城県、岩手県、福島県が特に被害が甚大で、茨城県、千葉県などでも多くの死傷者が出る事態となった。 この死者・行方不明者数は、明治以降の地震被害としては関東大震災の10万5,385人、明治三陸地震の2万1,959人に次ぐもので、阪神・淡路大震災の6,437人を大きく上回り、言葉を失ってしまう痛ましい災害となった。 |
(1)壁の配置と部材の緊結
①筋かいや面材(合板)で耐力壁をつくり、バランス良く配置する。
面材を柱や梁(軸組)の中にハメ込む方法もあり(プレウォール工法など)。
②建築基準法に則った必要壁量をバランス良く確保する。
③柱・梁・壁・床相互の緊結(有効な金物の選択)。




(2)重いものほど動く
テレビ、冷蔵庫、ピアノなど「重いものほど動く」。それも「激しく」ということを肝に銘じてほしい(「地震から生き延びることは愛」天野彰著 文春新書2005年)。 阪神・淡路や中越の地震で一番多かったのが、家具の転倒による死傷者だった。(同、天野彰) ⇒普段の生活のなかでは、重いものほど動かない感覚にとらわれがちだが、建物の地震対策以外に、本棚やテレビなど特に大型家具類の固定が地震時の安全確保のためには重要だ。
 2008年11月 東京駅復元・耐震(免震)工事
2008年11月 東京駅復元・耐震(免震)工事  2012年8月 グランドオープン前の東京駅
2012年8月 グランドオープン前の東京駅 九州国立博物館の免震装置
九州国立博物館の免震装置 構造的な補強が難しい歴史的建物や大規模な建築において、免震工法が採用される事例がたくさん見受けらますが、住宅にまでとなると、費用が掛かるなど難しい面があります。以下、「免震工事の評価」を、参考までに示します。
2009/09/26
免震工事の評価
⇒メリット
・大地震時の地震力は1/3~1/10に低減される。
建物の機能維持、家具の損傷防止、地震時のけが防止。
・建物に作用する地震力が小さくなるため、柱や梁のサイズを小さくできる。
設計自由度を高める。
⇒デメリット
・コストアップ(免震部材、免震ピットを設けること、フレキシブル設備配管等)
免震部材0.7~0.9万円/t
免震層躯体と土工事4~6万円/㎡
設備のフレキシブルジョイント400~500万円/棟
大臣認定を受けるための構造解析・調査費用1,500万円/棟
・免震建物は建築基準法の枠外なので、国土交通大臣の特認が必要。そのための時間と費用が掛かる。(財)日本建築センターで開かれる免震構造評定委員会に提出する資料を準備する時間、委員会の審議時間、認定書が発行されるまでの時間が掛かる。免震構造以外の設計図書を役所に先に提出し確認申請の作業を進めてもらっても、全体の確認には一般建物より1~2ヶ月余計に時間が掛かる。
・水平変位を拘束しないディテールが必要。
建物の周囲にクリアランス(50㎝~70㎝)が必要。
・免震部材の日常点検や定期点検(1年後、3年後、5年後、10年後、以降10年ごと)が必要。
60から70万円/回 他
※注意点
・免震部材の据付はクレーン等の重機による。
・免震部材の納期は普通サイズで3ヶ月程度。
建物は本来、耐震壁や筋交いなどで、がっちりと地震の揺れを抑えるだけでなく、その振動を家全体で吸収しています。日本古来の民家などの太い柱と梁を木組で構成する在来軸組み構造なども、構造が持っているこの機能によって、地震動に抵抗しています。
この点を積極的に取り入れて行こうという「制震」技術が今注目されています。
![]()